会計事務所×AIで属人化を解消――MCPで“つながる業務”に進化
- 2025年10月28日
- 読了時間: 13分
中小規模の会計事務所では、採用難・退職リスク・法改正対応・報告遅延などの課題が重なりやすく、現場は慢性的な残業と手戻りに悩まされがちです。多くの事務所では、税務・会計・給与といった基幹システム、顧問先管理、文書管理、コミュニケーション、さらにはAI-OCRやRPA(定型作業自動化)を個別導入していますが、それぞれが分断され「人が橋渡し」をする構造のままです。本記事では会計事務所におけるAI活用の中核として、MCP(Model Context Protocol)を軸に既存システムを安全に接続し、横断検索・自動要約・ドラフト生成・申請/承認までを一気通貫させる実践モデルを、具体事例とともに解説します。

会計事務所が直面する5つの壁
採用難や残業常態化が続くなか、多くの会計事務所ではツール導入が進んでも業務は“人の橋渡し”に依存し、生産性と品質の両立が難しくなっています。ここでは現場で頻発するボトルネックを5つの壁として再整理し、実際のシーンと失われるコストを具体化します。
1. 会計事務所の人材確保・定着の壁
面接では前向きだった新人が、繁忙期に記帳や請求書読取など“入り口作業”ばかりを担い、1年を待たずに離脱。育成担当は日中は顧客対応、夜に教育資料づくりで疲弊し、次の採用でも同じ負荷が繰り返されます。配属直後から残業が常態化し、成長実感より作業量が先に目に入る。経験者採用に切り替えても所内ルールや顧問先のクセに慣れるまで時間がかかり、結局は既存メンバーの肩に負荷が戻る――こうした悪循環が離職と採用コストの増加を招きます。
2. 属人化と引き継ぎ負荷の壁
「この申告はAさんでないと通らない」「B社はCさんしか履歴を把握していない」といった声は少なくありません。源泉徴収や消費税の論点メモが個人PCや私物ノートに点在し、退職・異動時の引き継ぎは“口伝”で長期化。担当交代で回答のニュアンスや根拠提示が揺れ、同じ問い合わせでも顧客満足度が安定しない。レビュー側も判断の背景が追えず差戻しが増え、休暇や体調不良が直ちに業務停止リスクにつながります。
3. 報告・案内コミュニケーションの壁
集計は終わっているのに、前年同月比や粗利率の変動説明、異常値の背景を文章化する段で手が止まり、所長コメントの確定が深夜にずれ込みます。送付が毎回ぎりぎりになり、意思決定のタイミングを逃すことも。さらに「どの書類をいつまでに、どのフォーマットで出してもらうか」が案件ごとにリセットされ、社内でも言い回しがばらつくため、毎回メールをゼロから作成。緊急度や影響度の優先順位付けができず、“一斉送信”か“個別フォロー”の二択に陥り、報告後の追い質問にも即応できない状況が積み重なります。
4. 手作業とシステム分断の壁
請求書の転記・科目判断・消込・二重チェックといった“間違えられない機械的作業”が延々と続き、締日前は机が紙で埋まります。一方で「財務会計」「税務申告」「給与」「顧問先・進捗」「文書管理」「コミュニケーション」「AI-OCR」「RPA」とシステムは増えたのに横断で見通せず、最新版ファイルの所在が不明確で複製が増加。AI-OCRの読取結果はこのシステム、突合の記録はあのシステム、最終連絡は別のシステムと履歴が点在し、状態確認だけで時間が溶けます。最終的に人のコピペで橋渡しするため、入力ミスや更新漏れが発生しやすい構造が残ります。
5. 法改正対応の後手化という壁
電子帳簿保存法やインボイス制度など、短期間で複雑な改正が続くなか、官公庁通達・専門誌・ベンダー通知と情報源が多岐にわたり、読む人ごとに解釈がズレます。所内マニュアルの改定は後回し、顧問先向け案内文は過去テンプレの継ぎ接ぎで暫定対応。影響範囲の洗い出しが遅れて「誰に何を先に伝えるか」が定まらず、問い合わせが増加。後追い説明に人員が割かれ、次の改正対応がさらに遅れる――“後手感”が常態化します。

会計事務所では、なぜ問題が繰り返されるのか
表面に現れる「遅延」「ミス」「離職」は、個々人の努力不足ではなく、所内に潜む構造的な要因が連鎖して生じます。とくに、情報が各システムに散在して横断できないこと、判断基準や手順が人に依存して言語化されていないこと、工程ごとのツールと管理単位が分かれて流れが分断されることが、再入力・手戻り・確認待ちを常態化させます。さらに、ナレッジの検索性が低いため教育に時間を要し、担当が替わるたびに品質が初期化され、法改正の情報も手作業で解釈・展開されるため周知のタイミングがずれます。以下で、これらのサイロ化/未形式化/工程分断/教育負荷/手動配信という5つの原因を具体的に掘り下げます。
情報のサイロ化(各システムに散在、横断検索不可)
会計、税務、給与、文書、進捗、コミュニケーションといったシステムごとに情報が分かれていると、「どこが最新版か」「誰の判断に基づくか」が曖昧になります。更新の起点が複数になるため、同一資料の複製や差分が増え、根拠確認に余計な時間がかかります。
さらに、横断検索ができなければ、作業者は都度ログインし直し、同じ語句で重複検索を繰り返します。結果として、再入力・転記・照合作業が常態化し、手戻りのたびに納期が押す――この遅延構造が「次の案件」へ累積し、慢性的な残業や疲弊を招きます。
暗黙知・ノウハウの未形式化(手順が人依存)
判断のコツや顧問先ごとの留意点が、個人メモやメール履歴に埋もれていると、属人化は避けられません。手順が文書化されていないため、同じ論点でも人によって解釈や表現が揺れ、レビューの差戻しや品質のバラつきが生じます。
また、参照すべき根拠や決裁の観点が明文化されていないと、経験の浅い担当者は確認のたびに上長を呼び止め、業務が断続的になります。ノウハウが流通しない環境では、退職や異動のたびに「ゼロからやり直し」が発生し、組織としての学習が蓄積しにくくなります。
ワークフローが点在し、前後工程がつながらない
記票→確認→登録→報告→周知と工程が分かれているにもかかわらず、各工程の進捗や成果物が別システムで管理されると、全体の状態が見えません。どこで滞留しているのかが把握しづらく、催促が後手に回ります。
工程間の引き継ぎが手動で行われると、抜け漏れが発生しやすく、次工程の着手が遅れます。加えて、各工程で使うフォーマットや粒度が揃っていないと、毎回整形や転記が必要になり、作業は分断・延長されます。結果として、納期直前の残業と品質低下が同時に起きます。
教育コストが高く、担当交代のたびに品質が初期化
学習素材が散在し、検索性が低い環境では、育成はマンツーマン依存になりがちです。教える側は本業と並行で時間を捻出し、教わる側は断片的に知識を得るため、理解が定着しません。
また、評価観点やレビュー基準が共有されていないと、担当が替わるたびに品質が揺れ、過去の水準に戻すための再教育が必要になります。引き継ぎ資料が体系化されていない場合、背景や判断根拠まで遡る作業が増え、短期的な生産性低下だけでなく、長期の育成効率も悪化します。
法改正のインプットから配信・周知までが手動
法改正情報は、官公庁資料、専門誌、ベンダー通知など複数ソースから流入します。収集・要点整理・影響範囲の特定・文例作成・承認・配信という一連の流れが手作業だと、解釈のばらつきとタイムロスが避けられません。影響度に応じた優先順位付けや、顧問先属性とのひも付けが後回しになるほど、案内の重複・抜け漏れが発生します。結果、問い合わせが増え、後追い対応に人員が割かれ、次の改正対応がさらに遅れる――こうして“遅延の連鎖”が固定化されていきます。

解決策:AI×MCPで「分断」を「連携」に変える
私たちが本当にやりたいのは、今ある会計・税務・給与や文書、進捗管理などのシステムを入れ替えることではありません。バラバラに散らばる情報をひとつの窓口で横断できるようにし、やり取りや承認も同じ流れの中で完結させることです。さらに、所内の正しい資料を土台に要点を自動で取りまとめ、報告書や案内文の“たたき台”を素早く用意できれば、探し物ややり直しは大きく減ります。言い換えると、「分断された道具を安全にまとめ、根拠に基づく下書きづくりまでを一気通貫にする“つなぐ仕組み”」が必要です。
それを実現してくれるのが、MCPという技術です。
MCPとは
MCPは、会話型アプリやエージェントが、外部の社内システムやSaaSに安全に接続して検索・操作するための標準的な接続仕様です。権限範囲を制御し、操作ログを残しながら、チャットUIから「会計・税務・給与」「顧問先管理」「文書管理」「AI-OCR」「RPA」に横断アクセスできます。つまり「既存システムを置き換えずにつなぐ」発想で、会計事務所×AIの効果を短期間で引き出せます。
▶︎MCPについて詳しい記事はこちらをご参照下さい!
会計事務所で明日から使えるAI活用の「5つのシナリオ」

顧問先問い合わせの一次応答をAIで自動化
顧問先からは、インボイス番号の確認や電子帳簿保存法の保管要件、領収書の取扱いといった似通った質問が繰り返し届きます。ここで、AIがRAG(社内文書などを検索して根拠に基づき回答を組み立てる手法)を用いて所内マニュアル、国税庁の公開資料、過去の回答履歴を横断参照し、参照元リンク付きの一次回答案を自動生成します。担当者は内容と根拠を確認したうえで、ワンクリックで返信できるため、H事務所では一次回答の所要時間が平均30分から5分へ短縮されました。加えて、やり取りからFAQの更新案が自動で下書き化されるため、知見が蓄積・循環しやすくなります。運用面では、回答ごとに根拠提示を必須とし誤回答リスクを抑制。承認フローや送信記録はMCP(既存システムを安全につなぐ仕組み)経由で業務ボードへ自動保存され、誰がいつ何を承認・送付したかが追跡可能になります。
月次報告ドラフトの自動生成
月次・年次の報告づくりでは、試算表から要点を抜き出し、前年同月比や粗利率の変動を整理し、異常値の背景説明や次月の留意点まで文章化するのに時間を要しがちです。そこで、AIが総勘定元帳や試算表のデータを読み込み、KPIサマリー(売上・粗利・費用の主要指標)、異常値の候補、担当者コメントの雛形、さらに所長総括の草案までを自動で生成します。これにより、担当者は「下書きの確認と補足」に専念でき、初稿作成は従来の約2時間から15分程度へ短縮。レビューに回る時間と集中力に余裕が生まれ、結果として顧問先への報告遅延が減ります。運用上のポイントは、異常値の根拠となる仕訳行や関連証憑へのリンクを自動添付することです。数字の背景と参照元が即時に示されるため、説明責任を担保しつつ、レビューと意思決定のスピードも引き上げられます。
法改正アラートと影響範囲の自動抽出
新制度や通達が出るたびに、「どの顧問先に、どの程度の影響があるのか」を人手で判定していると、情報収集と突合に時間を取られ、周知が後手に回りがちです。そこで、AIが改正の要点を要約し、所内マニュアルの該当箇所と顧問先の属性情報(業種・規模・取引形態など)を自動で突き合わせます。影響度は「大・中・小」に分類され、優先度順に送るための案内文テンプレート(宛名・敬語の体裁、期限、必要添付の指示まで含む)を自動生成。担当者は内容を確認して差分を最小限に整えるだけで、即時に配信へ移れます。運用面では、案内文の定型をあらかじめ標準化しておくことが肝要です。配信はMCP(既存システムを安全につなぐ仕組み)を介してメール・チャット・文書管理へ同報し、誰に・いつ送ったかの記録も同時に残します。これにより、周知の初動が1~2週間早まり、対応漏れに起因するクレームが大幅に減少します。
AI-OCR×突合×例外処理で記帳自動化率を引き上げ
請求書処理では、読取→仕訳→科目判断→消込という一連の流れに手間がかかり、締日前は恒常的に時間が押しがちです。そこで、AI-OCRで請求書の明細(発行日・取引先・品目・金額・税率など)を自動抽出し、AIが勘定科目と税区分の候補を提示。会計データ(取引先マスタ、過去仕訳、締切・ルール)と突合して、矛盾や不足がある“例外”だけを人が判断します。確定後の登録はRPAで自動化し、担当者は例外対応と最終確認に集中できる運用へ切り替えます。これにより、読取から登録までのリードタイムはおおむね半減し、特に繁忙期の残業時間が目に見えて減少します。運用の要点は二つ。第一に、候補判定に信頼度のしきい値を設け、低スコア案件は必ず人手に回すこと。第二に、確定後の仕訳データを継続的に収集・蓄積し、次回以降の候補精度向上に活かすことです。ミスを抑えつつ処理量をこなす体制が整い、現場の負荷平準化にもつながります。
進捗管理ボットで滞留を可視化・催促を自動化
顧問先対応の現場では、タスクは顧問先管理ツール、資料は文書管理、連絡はチャットと分散し、全体の進捗が把握しづらくなりがちです。結果として、誰がどこまで終えているのか、承認待ちがどこで滞っているのかを把握するだけで時間がかかり、期限超過や報告の抜け漏れにつながります。そこで、MCP(既存システムを安全につなぐ仕組み)で進捗ボード・文書管理・チャットを接続し、未着手・期限超過・承認待ちをボットが日次で自動集計。担当者と所長へ状況通知を行い、該当タスクや文書、スレッドへワンクリックで遷移できる導線を整えます。これにより、滞留の早期発見が常態化し、期限厳守が組織の標準行動として定着。結果として、報告の“抜け漏れ”が目に見えて減少します。運用面では、通知過多による“アラート疲れ”を避けるため、週次/日次の切り替えや閾値を調整し、KPI(期限遵守率、滞留件数、承認リードタイムなど)と紐づけて改善サイクルを回すことが重要です。
これらのシナリオは、御社で導入済みのシステム環境によって、実現のしやすさが変わってきます。 「これ、うちでも実現できるかも?」「こういう働き方ができたら本当に助かる!」と感じられた方は、ぜひスノーリーズ株式会社までご相談ください。導入可能性を丁寧にヒアリングし、最適な提案をさせていただきます。
スモールスタートで“勝ち筋”を作る
最初から全連携を狙う必要はありません。おすすめは「入口の自動化+報告の初稿自動化」の二点集中です。AI-OCR×例外処理で入口工数を削減し、月次ドラフト自動生成で出口スピードを上げると、体感価値が最短で伝わります。さらに、MCPで既存SaaSを“つなぐだけ”の構成にすれば、入替コストや教育コストも抑えられます。パイロットで成果を数値化し、対象顧問先と業務範囲を拡大する段階戦略が、投資回収に直結します。
まとめ・今後のアクション
会計事務所の現場課題は、個々のツール導入では解消しきれません。鍵は「AIで賢くする」だけでなく、「MCPで既存システムを安全につなぐ」ことです。入口のAI-OCR×例外処理、出口の月次ドラフト生成、そして横断検索・承認まで一気通貫にすることで、属人化の解消、報告スピードの向上、教育負荷の軽減を同時に達成できます。
会計事務所の現場課題は、「AIで賢くする」より先に、「いま使っている会計・税務・給与や文書、進捗の仕組みを安全につないで、同じ土俵で回す」ことが突破口になります。入口ではAI-OCR+例外処理で入力の山を抑え、出口では月次レポートの初稿を自動で立ち上げ、間をつなぐ横断検索と承認を同じ流れに収める。これだけで、属人化のしこりがほどけ、報告の初速が上がり、教育の“やり直し”も減ります。個々の改善は小さくても、つながった瞬間に効果は面で立ち上がる――小さな改善が繋がることで、その有効性は実務レベルで裏づけられていくことを感じていただけると思います。
今日からできる3ステップ
ボトルネック特定(入口の手入力/出口のドラフト作成など)
代表ユースケースを1つ選び、RAGと参照元提示を前提に設計
MCPで必要最小限の接続を試し、2〜3社でパイロット実施
本記事の実装例は、横断連携と参照元提示を重視するAIboxで短期間に検証できます。AIboxは、会計・税務・給与、顧問先管理、文書管理、AI-OCR、RPAなど既存システムと連携し、RAGにより根拠リンクつきの回答や報告ドラフトを生成。MCPを活用して会話UIから安全に検索・操作でき、属人化の排除と迅速な顧客応対を支援します。まずはパイロットから、貴所に最適な“勝ち筋”を一緒に設計しましょう。
詳細・ご相談:https://www.ai-box.biz/
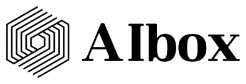
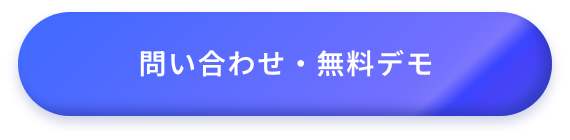




.jpg)
コメント