NTTとトヨタが描くモビリティの未来:AIで交通事故ゼロ社会への挑戦
- 石黒翔也
- 2024年12月2日
- 読了時間: 8分
2024年10月31日、NTTとトヨタ自動車は共同記者会見を開催し、「交通事故ゼロ社会」の実現を目指す新たな協業について発表しました。この記者会見には、日本電信電話株式会社(NTT)の島田明社長と、トヨタ自動車株式会社の佐藤浩司社長が出席し、両社の取り組みや技術的なビジョンを詳しく説明しました。
協業の背景と目的:交通事故ゼロ社会への歩み
佐藤社長は、NTTとトヨタが目指すビジョンとして「交通事故ゼロ社会の実現」を掲げ、そのための基盤としてモビリティAI通信を活用する重要性を強調しました。
これまで両社は、2017年からコネクテッドカーのデータ処理基盤開発に取り組み、2020年にはスマートシティ構築をテーマに協業範囲を拡大してきました。今回の発表はその延長線上にあり、さらなる技術革新を通じて、モビリティと社会基盤の融合を実現する次なるステップです。
特に佐藤社長は、交通事故ゼロ社会を牽引する「ソフトウェア・ディファインド・ビークル(SDB)」という新たな車両概念を紹介。SDBは、車両の電子制御システムを刷新し、必要なデータを効率的に収集しAIで解析することで、事故防止や安全性向上を目指します。
モビリティAI通信基盤の構築:三味一体型のインフラ協調
今回の協業の核心となるのは、モビリティAI通信基盤の構築です。これは、車両とインフラ、人々をつなぐ三味一体型のインフラ協調を実現するもので、以下の3つの基盤から成り立っています。
分散型計算基盤トヨタはNTTのアオ技術を活用し、膨大な計算量を処理するための分散型データセンターを設置。2030年には通信量が22倍、計算量が150倍になると予想される中で、この基盤は社会の変化に対応する重要な要素です。
次世代通信基盤車両やインフラから収集される膨大なデータをリアルタイムで処理するため、AIが最適な通信手段を選択。切れ目のない高速通信を提供する次世代通信基盤がその役割を果たします。
AI基盤分散型計算基盤と次世代通信基盤を活用して収集されたデータを元にAIモデルを開発。これにより自動運転技術やAIエージェントの導入が進み、新たなモビリティサービスが提供される予定です。
データドリブン開発とインフラ協調
交通事故ゼロ社会の実現に向け、佐藤社長は「データドリブン開発」と「インフラ協調」の2つのアプローチを提案しました。
データドリブン開発
AIを活用して市場での走行データを継続的に学習し、シミュレーションの精度を向上させます。これにより、ソフトウェアの迅速なアップデートが可能となり、車両の自律型制御性能が高められます。
インフラ協調
車両がインフラや他の車、人々から情報を収集することで、視覚の死角を減らし事故を予防。また、AIが収集したデータをもとに予測精度の高い運転支援を行い、市街地、高速道路、郊外などのさまざまなシーンで安全性を向上させます。
NTTの技術的ビジョンと役割
続いて登壇したNTTの島田社長は、AI通信基盤を支える具体的な技術について説明しました。NTTが構想する「アイオ(IO)」は、以下の3つの技術基盤から構成されます。
高速・低遅延ネットワークワイヤレスネットワークとオールオプティカルネットワークを活用し、車両や人々からの膨大なデータを低遅延で処理。
デジタルツインコンピューティング収集したデータをシミュレーションすることで、モビリティ社会を先読み。精度の高い予測と社会の最適化を目指します。
コグニティブファンデーション各基盤を効率的に連携させ、低消費電力でデータ収集と処理を行う仕組みを提供。
さらに、NTTはグローバルなネットワークとデータセンターの運営経験を活かし、モビリティ社会を支える基盤の拡張を計画しています。
ロードマップと今後の展望
両社は本日よりモビリティAI基盤の開発を開始し、2028年頃から社会実装を本格化させる予定です。また、2030年までに約5000億円規模の投資を行い、モビリティ社会の普及拡大を目指します。
最後に島田社長は、「NTTとトヨタが協力し、住み良い地球と豊かな社会を作り上げたい」と述べ、協業に賛同する仲間を増やし、未来のモビリティ社会を実現していく決意を表明しました。
質疑応答
質問1:三味一体の意味と交通事故ゼロ社会の課題
質問者:「車と通信が組む意義について、三味一体という表現の意味も含めてご説明いただきたい。また、交通事故への課題感や実現したい社会像についても教えてください。」
回答(佐藤社長):「三味一体とは、車、通信、インフラが一体となることで安全で快適なモビリティ社会を実現するという考えです。これまで車両単体で進化してきた技術を、より高度に進化させるためには、通信と一体となった社会基盤の構築が必要不可欠です。また、交通事故ゼロ社会の実現に向けては、リスクの先読みが重要です。これにより、予測型の運転支援を強化し、安全安心な社会を目指します。」
質問2:自動運転の開発方針
質問者:「世界では無人運転を目指した自動運転の開発が進んでいますが、トヨタの考える自動運転の開発軸について教えてください。」
回答(佐藤社長):「自動運転は、安全安心なモビリティ社会を作るための手段と考えています。私たちは、人を中心に据えた運転支援を軸に開発を進めており、完全な自動運転ではなく、人が中心であることを大前提としています。これにより、多くの移動の自由を獲得し、段階的に高度な運転支援を実現していきます。」
質問3:モビリティAI基盤の標準化と展開
質問者:「今回の取り組みで述べられた標準化は、国内に限定されるのか、それともグローバル展開を視野に入れているのか。また、その道筋についても教えてください。」
回答(島田社長):「モビリティAI基盤はまず国内で基盤を作り、そこからグローバル展開を目指します。各国の規制や交通環境、通信環境を考慮し、標準化を進める必要があります。この基盤は多くのパートナーと連携して作り上げるものであり、グローバルに展開できるインフラとして発展させたいと考えています。」
質問4:ウーブンシティとの関係
質問者:「三味一体型のインフラ協調は、ウーブンシティのコンセプトと重なる部分があると思いますが、この取り組みがウーブンシティで実証される予定はありますか?」
回答(佐藤社長):「ウーブンシティは、人を中心にした街づくりとモビリティのテストコースとしての役割があります。この取り組みの具体的なテーマが決まれば、ウーブンシティでの実証を進めていきたいと考えています。」
質問5:パートナーシップの方向性
質問者:「2028年頃からパートナーと進めるとのことですが、具体的にどのような業種のパートナーを想定していますか?」
回答(島田社長):「モビリティAI基盤を構築するには、通信事業者やソフトウェア開発者、インフラ関連の企業など、さまざまな分野のパートナーとの協力が必要です。グローバル展開においても、多くの企業が参画しやすい仕組みを作りたいと考えています。」
質問6:ユーザーコストへの影響
質問者:「今回の取り組みで、ユーザーコストが増加する可能性はありますか?」
回答(佐藤社長):「モビリティAI基盤は社会基盤として広く普及させるもので、ユーザーコストを極力抑える方向で検討しています。基盤が整うことで、車両側での負担が軽減される可能性があり、トータルでのコスト効率を向上させることを目指しています。」
質問7:AIエージェントの具体的な役割
質問者:「AIエージェントは、人にどのような支援を行い、どんなHMI(ヒューマン・マシン・インターフェース)を提供するのか教えてください。」
回答(佐藤社長):「AIエージェントは、人の行動やバイタル情報を統合的に分析し、適切なガイダンスを提供します。例えば、渋滞時の合流やブラックアイスバーンの注意喚起など、ドライバーの判断を補助する形で高度な安全性を実現します。」
質問8:グローバル展開の課題
質問者:「モビリティAI基盤をグローバルに展開する際、中国やロシアのような国々はどのように扱われるのでしょうか?」
回答(島田社長):「価値観を共有するパートナーと連携しながら進めることが重要です。現状の政治情勢を考慮しつつ、共有可能な価値観を基に協力体制を築いていきたいと考えています。」
質問9:5000億円投資の具体的な内訳
質問者:「2030年までに予定されている5000億円規模の投資は、どのような分野に配分されるのでしょうか?」
回答(島田社長):「分散型計算基盤、AI基盤、次世代通信基盤の3つに投資されます。特に計算基盤の開発に大きな割合が割かれる見込みですが、各分野が相互に支え合う形で進められます。」
AIboxのご紹介
AIboxは、NTTやトヨタが進めるような次世代技術の活用と同じく、最新のAI技術を用いて社内問い合わせ対応を自動化し、業務効率を劇的に向上させます。

RAG機能で高精度な回答が可能 「AIbox」はRetrieval-Augmented Generation(RAG)という技術を搭載。社内のマニュアルや過去の問い合わせデータ、FAQなどを参照して、内容に基づいた精度の高い回答を提供します。これにより、従来のチャットボットよりも使いやすく、頼れるサポートが実現します。
スムーズな社内コミュニケーション 社内でよく利用されるSlackとの連携機能により、AIboxはSlack内の情報も検索対象にすることが可能です。例えば「経費申請の締め切りを知りたい」といった質問も、Slackから直接AIに問い合わせることで即座に回答を得られ、業務が止まることなく進みます。
徹底サポートと安全性 AIboxは、Azure OpenAIサービスを活用した高いセキュリティ性も特徴です。利用データが外部のOpenAI社に送信されることはなく、企業内の機密文書も安心して取り扱うことができます。さらに、導入時や運用後のデータ整備についても専門スタッフが支援し、スムーズな導入と安心運用が可能です。
こんな部門での活用が進んでいます
経理、総務、人事などのバックオフィス:各部門で必要なFAQやマニュアルをAIboxに登録することで、社員からのよくある問い合わせ対応が自動化され、日常的な業務負担が軽減されます。
カスタマーサポート:エクセルや問い合わせ履歴などのデータをAIに読み込ませておくことで、過去の対応履歴から適切な回答をAIが自動生成。お客様からの問い合わせに、的確で素早い回答を提供できます。
問合せ先
スノーリーズ株式会社について
バックオフィス向けソリューション AIboxについて
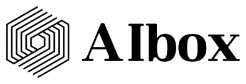
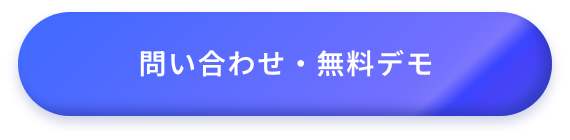





.jpg)
コメント